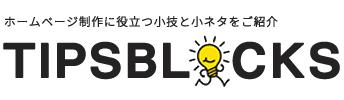ヒアリングの失敗が招く“ズレた設計”の事例集
〜初心者でも学べる、ホームページ設計の落とし穴と対策〜
はじめに:その“ズレ”、最初から避けられたかもしれません
ホームページ制作において「思っていたのと違う……」という経験をしたことはありませんか?
これは制作者の技術不足やデザインセンスの問題だけでなく、最初の“ヒアリング”に原因があることが少なくありません。
ヒアリングとは、依頼主の要望や目的、ビジネスの特性などを聞き取り、それを設計やデザインに反映するための大切なプロセスです。
この記事では、よくあるヒアリングの失敗と、そこから生じた「ズレた設計」の事例を紹介しながら、どうすれば防げるかを初心者にも分かりやすく解説します。
よくあるヒアリングミスと“ズレた設計”の事例
■ ケース1:ターゲットが曖昧なまま進行
事例:オシャレなカフェのホームページが、誰にも刺さらない
地方都市で営業する個人経営のカフェから、「とにかくオシャレに」と依頼され、トレンド感のあるデザインで制作。
しかし公開後、アクセスも来店数もほとんど増えませんでした。
どこがズレた?
ヒアリング時に「ターゲットは?」という問いに対し、依頼者に明確な答えがなかったことが原因でした。
解決のヒント
- 具体的なペルソナ(例:20代女性、子連れのママ、仕事帰りの会社員)を設定する
- その人物像が求める情報をページに反映する
■ ケース2:事業の目的が共有されていなかった
事例:SEO対策済みでも検索に出てこない士業サイト
「問い合わせを増やしたい」と依頼した行政書士。しかし実際には「地元での認知を強めたい」という意図があった。
どこがズレた?
制作側が「全国対応での集客」と誤解し、地域名を重視しなかった点がミスでした。
解決のヒント
- 集客エリアを明確にする(例:「○○市」「○○駅周辺」)
- ローカルSEOを意識したキーワード選定をする
■ ケース3:運用者のスキルに合わない設計
事例:ワードプレスを導入したが、ITが苦手で更新されない
ハンドメイド作家が「自分で更新したい」と希望。ワードプレスを導入したが、依頼者がログインすらできず、更新がゼロに。
どこがズレた?
「自分で更新したい」という言葉をそのまま信じ、ITスキルの確認を怠った点です。
解決のヒント
- ヒアリング時にITリテラシーの確認を行う
- 簡単な更新方法や代行サービスの提案をする
■ ケース4:好み重視のデザインが目的とズレる
事例:かわいくてポップなネットショップ、でも売れない
依頼者の「カラフルで楽しいデザインが好き!」という要望を反映。閲覧数は増えたが、購入に至らず。
どこがズレた?
好みに合わせた結果、導線が複雑になり、購入までたどり着けないユーザーが多かった。
解決のヒント
- デザインは「好み」ではなく「目的」に合わせて設計する
- 訪問者の行動を明確に想定する(例:「買ってもらう」など)
■ ケース5:業務理解不足がもたらす構成ミス
事例:専門用語ばかりで何のサービスか分からない
コンサルタントのサイトに業界用語を多用し、初心者が理解できず離脱。
どこがズレた?
制作者が、業界外の人には難しいと気づかず専門用語をそのまま使用してしまった。
解決のヒント
- 業界外の人にも伝わる平易な言葉を選ぶ
- 顧客の知識レベルを事前に確認する
■ ケース6:競合リサーチ不足による差別化失敗
事例:同業他社と似たようなデザインで埋もれるサイトに
整体院を営む個人事業主が「プロっぽくて安心感のあるデザイン」を希望し、よくあるブルー系のサイトを制作。
結果、検索結果やSNS上で同業他社のサイトに埋もれてしまい、問い合わせが増えなかった。
どこがズレた?
依頼者の「安心感」という抽象的な表現をそのまま受け取り、他サイトと差別化できないデザインにしてしまった。
解決のヒント
- ヒアリング時に「競合と何が違うのか?」を深掘りする
- 視覚的にもコンテンツ的にも“差別化ポイント”を明確に
■ ケース7:スマホユーザーの閲覧環境を想定していなかった
事例:見た目は良いが、スマホでの操作性が最悪
美術系のポートフォリオサイト。
依頼者がパソコン画面での見栄えにこだわり、デスクトップ優先で設計されたが、スマホでは表示が崩れ、文字も読みにくい。
結果、多くのスマホユーザーが離脱。
どこがズレた?
実際の閲覧者の多くがスマホでアクセスすることを想定していなかった。
解決のヒント
- ヒアリング時に「ユーザーの閲覧環境」を確認する
- レスポンシブデザイン(※画面サイズに応じて表示が最適化される設計)を必須とする
■ ケース8:サイト構成が依頼者の頭の中基準になっていた
事例:本人は分かっているが、訪問者には分からない構造
専門職の方が自身の実績や経歴を細かく分類し、複雑な構成のホームページを希望。
そのまま制作した結果、訪問者は「何から見ればいいか分からない」と迷子状態に。
どこがズレた?
依頼者自身には馴染みのある構成でも、初見のユーザーには不親切だった。
解決のヒント
- ユーザー視点での導線設計が重要
- 「他人に見せたときに迷わないか?」を必ず確認
■ ケース9:デザインの自由度を過信した結果、制約を見落とす
事例:決済サービスや予約システムが後付けで入らない
カウンセリングサービスのホームページ。
デザイン先行で制作したため、後から「決済機能を追加したい」となった際にシステム的に大きな改修が必要となった。
どこがズレた?
将来的な拡張を見越さず、短期的なデザイン性だけで設計してしまった。
解決のヒント
- ヒアリング時に「今後やりたいこと」も聞く
- 柔軟に拡張できる設計を前提に構築する
■ ケース10:写真や素材の準備が甘く、デザインが活かせない
事例:高品質なデザインなのに、画像が暗くて魅力半減
美容室のホームページで、デザインは洗練されていたものの、提供された店舗や施術の写真がスマホで撮影された暗い画像ばかり。
結果、仕上がりがチープな印象に。
どこがズレた?
「写真は自分で用意します」という言葉をそのまま信じ、品質チェックを怠った。
解決のヒント
- ヒアリング時に「写真のクオリティ」に関する認識を共有
- 必要であればプロの撮影や画像加工も提案
まとめ:ヒアリングとは“設計図”を描くこと
ヒアリングとは単に話を聞くことではありません。
- どんな人に届けたいのか
- その人は何を知りたくてページに訪れるのか
- 依頼者はどう運用したいのか
こうしたポイントを一つひとつ丁寧に確認することで、ズレのないホームページが実現できます。
ホームページは作って終わりではありません。長く使える“資産”として活かすためにも、最初のヒアリングが成功のカギを握っています。
次回は、「“頼んでみたけど失敗した”発注者の本音と、その背景」について掘り下げていきます。