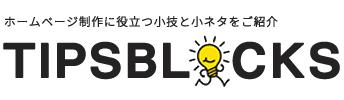外国人対応行政書士の「やさしい日本語」の書き方入門
「日本に住む外国人の数は年々増加している。」
もはやこれは、ニュースではなく“前提”になりつつある事実です。
観光客や短期滞在者とは異なり、在留資格を持ち、日本の社会に長く根ざしていこうとする外国人たち。彼らにとって、行政手続きの壁は想像以上に高く、そしてその案内を担う行政書士や司法書士といった士業の存在は、ますます重要になっています。
しかし、ここに1つの大きな課題があります。
それは「言葉の壁」です。
この記事では、「外国人対応を強化したい行政書士」や、「士業として今後、外国人との接点が増えそうだ」と感じている方に向けて、今注目されている「やさしい日本語」というコミュニケーションの手法を中心に、その考え方、導入方法、そして実務での活かし方まで、詳しく解説していきます。
「やさしい日本語」って何?
「やさしい日本語」と聞いて、多くの人がまず思い浮かべるのは「小学生でもわかるような日本語」というイメージではないでしょうか。
それも間違いではありませんが、正確には少し違います。
やさしい日本語とは:
災害時や公的情報の伝達など、母語が日本語ではない人でも理解できるように、文法や語彙(ごい)を簡単にし、わかりやすくした日本語のことです。
元々は阪神・淡路大震災(1995年)を契機に生まれた概念で、外国人にも迅速に正確な情報を伝えるために、専門用語や難解な表現を避けた日本語の使用が求められたことから広まりました。
今では、防災情報、行政窓口、医療現場、そして外国人労働者の受け入れが進む中で、企業や士業の現場でも積極的に取り入れられ始めています。
「やさしい日本語」と「外国人向け英語」の違い
「どうせなら英語で案内すればいいのでは?」と思う方も多いかもしれません。
確かに、英語を併記する方法も広く行われていますが、以下のような現実があります。
- 在日外国人の中で英語を理解できる人は必ずしも多くない
- 技能実習生や留学生など、母語がベトナム語、インドネシア語、ミャンマー語などの場合、英語よりも日本語の方が理解されやすいケースもある
- 外国人向け行政支援では、翻訳にかかるコストや手間が大きくなる
つまり「英語=万能」ではないのです。
一方で「やさしい日本語」は、“翻訳ではなく調整”です。
日本語というベースを使いながら、少しだけルールを変えることで、より多くの外国人に届く情報の形をつくれるのです。
行政書士業務における「やさしい日本語」の活用例
では、具体的に行政書士の現場ではどう使われているのでしょうか?
以下に典型的なシーンを挙げてみます。
① ビザ関連手続きの説明文書
例(通常の文):
本在留資格は、就労活動が許可されておらず、原則として報酬を受ける活動を行うことはできません。
例(やさしい日本語):
このビザでは、働くことができません。お金をもらって仕事をすることは、基本的にできません。
② 案内メールやLINE
例(通常の文):
次回のご来所予定は、以下の日時で問題ありませんでしょうか。
例(やさしい日本語):
つぎの相談は、この日にちでいいですか?
③ ホームページやパンフレットの文言
例(通常の文):
永住申請の要件について、以下に詳しくご説明いたします。
例(やさしい日本語):
永住(えいじゅう)の申請(しんせい)のルールを、これからわかりやすく説明(せつめい)します。
④ 面談中の会話
例(通常の文):
該当する資料をご準備いただき、事前にご送付いただけますでしょうか?
例(やさしい日本語):
ひつような書類(しょるい)を用意(ようい)してください。あとでメールでおくってください。
「やさしい日本語」導入の3ステップ
ステップ1:まず自分の言葉に気づく
自分が普段どれほど専門用語を使っているか、意外と気づきにくいものです。
例えば、
- 報酬 → お金
- 書類 → かみ
- 提出 → だす
など、士業にとって当たり前の言葉が、外国人にとっては難解であることを意識するところから始まります。
ステップ2:「ひらがな化」と「短文化」の習慣化
- 難しい漢字には( )でふりがなをつける
- 1文を短くする(1文1情報)
- 「〜することができます」より「〜できます」と簡潔に
こうした意識を持つことで、文章全体の可読性が劇的に向上します。
ステップ3:実際の外国人に読んでもらう
言語とは“生きたもの”です。
実際に外国人クライアントに説明文を読んでもらい、どこが難しかったか、どこでつまずいたかをフィードバックしてもらうことが、最大の改善材料になります。
よくある誤解と注意点
誤解①:「やさしい日本語」は失礼?
敬語や丁寧語を避けると、ぶっきらぼうになってしまうのでは?という不安を持つ方も多いのですが、「やさしい日本語=ため口」ではありません。
やさしい日本語の基本は、「わかりやすく、ていねいに」です。
たとえば、
- ×「ダメです」 → ○「できません」
- ×「それはムリ」→ ○「それはできないかもしれません」
やさしさとは、言葉のトーンに現れるものなのです。
誤解②:「誰にでも通じるわけではない」
やさしい日本語は万能ではありません。
母語の習得レベルや日本語学習歴によって、理解のレベルは異なります。
そのため、場合によっては英語表記や多言語対応も必要になります。
しかし、最初の一歩としては、やさしい日本語が最も手軽で実用的である点に変わりはありません。
他士業でも活かせる「やさしい日本語」
この記事は行政書士を主軸にお話ししていますが、「やさしい日本語」はあらゆる士業で活かすことができます。
- 司法書士:不動産登記や相続手続きの説明に
- 税理士・会計士:確定申告や帳簿の説明書きに
- 社労士:雇用契約や労働条件の理解支援に
- 弁護士:契約書の内容確認や初回相談時の対話に
つまり、「外国人対応=行政書士だけの仕事」ではないのです。
ホームページと「やさしい日本語」
ここまでお読みいただいた方の中には、「自分の業務にもやさしい日本語を取り入れたい」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
近年では、士業のホームページにも「やさしい日本語版ページ」を設ける事務所が増えてきました。
しかもその動きは、SEO(検索エンジン最適化)対策や、SNSなどを通じた拡散戦略にもリンクしています。
- やさしい日本語でのQ&Aページ
- やさしい日本語での「業務内容紹介」
- 多言語リンクの中に「やさしい日本語」も含める
こうした工夫が、やがて士業のブランディングや差別化の要素にもなってくるでしょう。
おわりに:「やさしさ」は最も強い武器になる
ビジネスにおいて、よく「強みを打ち出すこと」が語られます。
しかしこれからの時代、本当の意味で信頼を得られるのは、「相手の立場になって考えられる力」=やさしさ、なのではないでしょうか。
「やさしい日本語」は、その最たる表現手段の1つです。
専門性を武器にする士業にとって、「やさしさ」という視点を文章に落とし込む力は、これからの時代にこそ不可欠なスキルかもしれません。