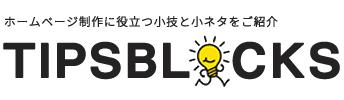「とりあえず作る」ホームページの落とし穴|成功する発注のコツとは?
はじめに:なぜ「とりあえず作る」から失敗するのか
「そろそろホームページが必要だと思って…」「知人から“今どき持ってないの?”と言われて…」。そんな気持ちで“とりあえず”始めたホームページ制作、実はかなりの確率で失敗しています。
原因はシンプル。目的が曖昧なままスタートしてしまうからです。
本記事では、そんな“とりあえず”スタートの危うさと、成果につなげるために必要な事前準備の視点を、実例を交えて徹底解説します。
第1章:「目的がふわっとしている」と全てがブレる
■ よくある状況
「とりあえず会社案内みたいな感じで…」という依頼、制作会社側もよく受けます。
ですがこの時点で「誰に」「何を」「どう感じてほしいのか」が抜けていると、全体の構成がぼやけてしまいます。
■ 具体例:B社の失敗ケース
製造業B社は“とりあえず”で会社紹介サイトを作りましたが、顧客からの問い合わせはゼロ。理由は、強みがどこにも打ち出されていなかったからでした。
■ 成功のための対策
- 「訪問者にどう行動してほしいか(KPI)」を明確にする
- ターゲットのペルソナを1人に絞る
- 目的を「採用用/営業用/既存顧客向け」など分けて考える
第2章:「情報設計なし」のツケは後からやってくる
■ よくある状況
「文章はあとで考えます」「写真は撮ってから送ります」──このような後回しの姿勢が、制作現場では大きなロスを生みます。
■ 問題ポイント
デザイン先行で進んでしまい、内容が追いつかず、結果的にサイトの完成度が下がる。
■ 対策:3点セットで情報を先に固める
- トップページに掲載すべきメッセージ
- サービス・料金などの具体的な構成
- 企業概要や沿革、スタッフ紹介
特に“売り文句”や“選ばれる理由”は、発注者側で言語化できているかどうかが重要です。
第3章:「公開して終わり」にしないために
■ よくある状況
「まずは公開」「後からブログは書くつもりでした」──しかし多くの場合、更新されないまま時間が経ってしまいます。
■ 問題ポイント
更新されないサイトは、SEOにもユーザー信頼にも悪影響。
■ 成功する運用のコツ
- 最低限の更新スケジュール(月1回のニュース・ブログなど)を決める
- 誰が何をどのように書くか、事前に役割分担を決める
- 更新しやすいWordPressテンプレートや投稿ルールを設計しておく
補足:とりあえず作って後悔したC社のケース
C社(士業)は知人の紹介で制作会社に依頼。「とりあえず名刺代わりに」という発注で、構成も文章も制作側に丸投げ。結果、公開してもまったくアクセスが伸びず、半年後に別会社にリニューアルを依頼。
制作側としては「目的が不明」「文章がない」「実績も分からない」状態では、成果の出るサイト設計ができません。これは“安いけど成果ゼロ”の典型です。
まとめ:「とりあえず」から「計画的」へ
ホームページ制作は、名刺のような“置いておくだけ”のツールではありません。
何のために、誰に向けて、どんな成果を狙うのか。 これを明確にすれば、制作会社側も力を発揮しやすくなり、完成後の運用にも手応えが出てきます。
「とりあえず」から、「計画と意図ある発注者」になる──それが、成果を上げるホームページの第一歩です。